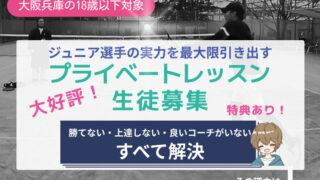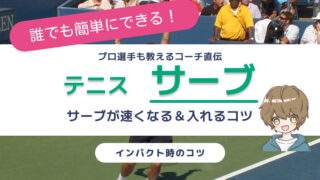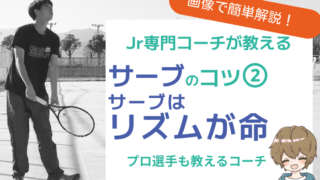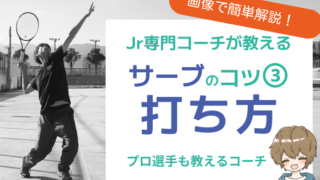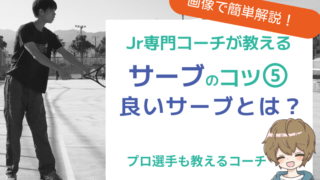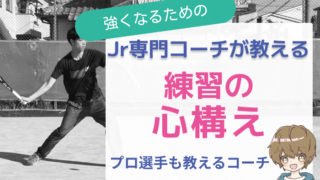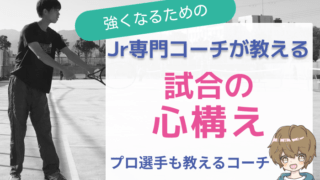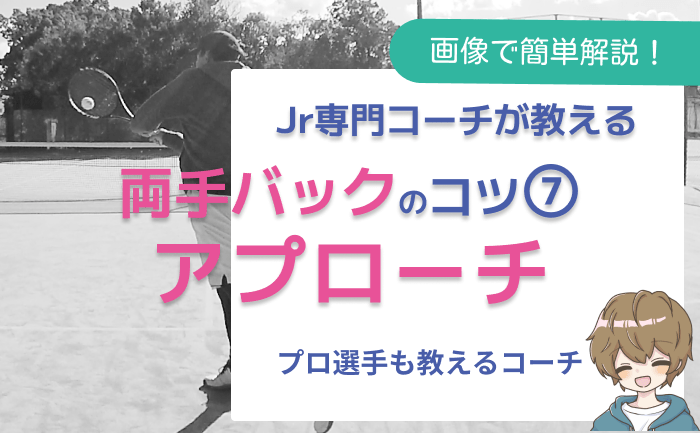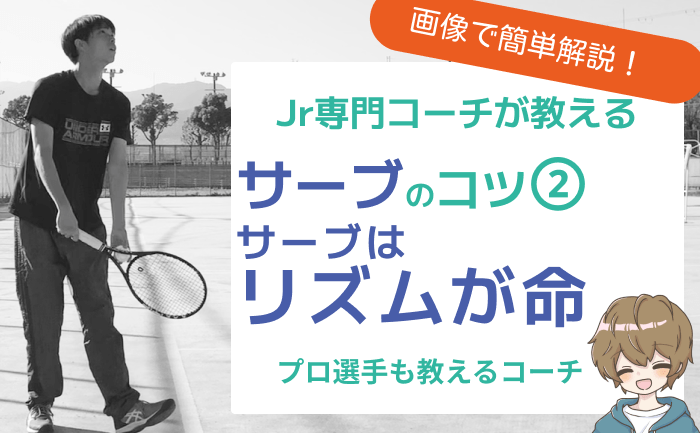サーブのイメージ動画。
ブログの解説を読みながら観るとよく分かると思います!
・サーブの打ち方が知りたい!
・もっと強いサーブが打ちたい!
・もっと入るサーブが打ちたい!
① サーブの基本がわかる
② 勝つためのサーブが打てるようになる
③ フラットサーブが打てるようになる
④ スライスサーブが打てるようになる
⑤ スピンサーブが打てるようになる
⑥ 格段に強く入るサーブが打てる
⑦ サーブが楽しくなり打ちたくなる
⑧ 本当のサーブの知識が得られる

こんにちは!ぐっど(@good__tennis)です!
①はじめての教え子はプロ選手に。
②プロ選手の復調を複数人指導した経験あり、得意。
③本戦選手を多数育成。
④小学高学年から、コーチングをする。
⑤選手のメンタル強化も得意。
⑥公立の外部コーチの経験あり。
⑦プロ選手専属のストリンガーの経験あり。
⑧ジュニア専門コーチ歴20年以上。
今回は、「サーブ」をシリーズで徹底的に解説します!
構え方・大切なリズム・打ち方の基本・ボールのとらえ方・フラットの打ち方・スライスの打ち方・スピンの打ち方・良いサーブとは?の考え方まで、強くなるためのサーブをすべて解説!
特にスピンサーブの打ち方は、私以外では教えていないモノです。
プロ選手も上手く強くできるコーチだからこその解説を、楽しみながら読んでくださいね!
「テクニック」は頭を納得させ、「基本」は心を納得させる。
テクニックは大切ですが、もっと大切なのは基本です。
基本を習得すると、テクニック(応用)はむずかしくありません。
問題は、基本技術だと思っていたのに、応用を教えられていた場合です。
これは、本物のコーチでないと分かりません。
基本ができれば、すぐに勝てるようになります。私は実際に教え実績もあるので確信があります。
今回は、『サーブその1・サーブの構え方』についてです。
一番簡単にサーブを強くし、入るようにしたい方は、下のサーブ・インパクトのコツをご覧ください!
誰でも簡単にできる内容になっています!
足の構え方
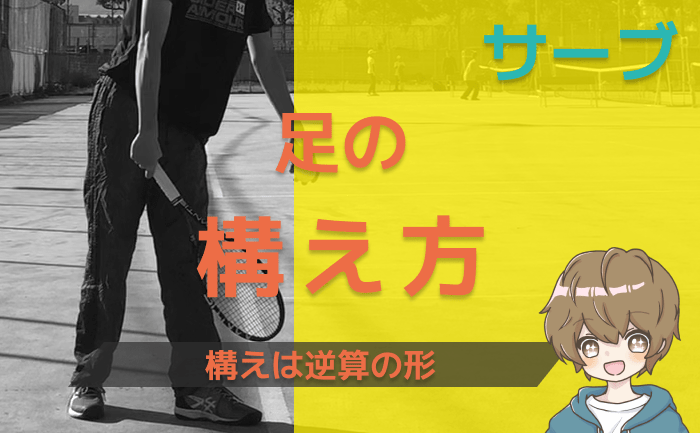

では、「両足の形」みていきましょう!
両足の形
構えたときの両足の形を、まず下の画像でご覧ください。
なぜこの形かというと、日本人がサーブの打点に対して最小の労力で、最大のパワーを出せるように考えられた形だからです。
つまりボールに、最大のパワーを乗せられるようにした形。

体が向く方向は、打点〜打ちたい方向の間にします。
よく横をプロ選手の真似をして、真横を向いて打つ人がいますが、プロ選手でしかも欧米人のサーブや打ち方を、日本人であり素人が真似をしても、パワーの乗ったサーブは絶対に打てません。
それは、まずプロ選手のほぼ全員が、自分に合った独自の形に変化させているからです。つまり基本ではありません。ものすごく大切な知識ですので、最後に詳細に説明しています。
上記に加えて、欧米人と日本人では体の造りが違います。つまり「強み」がまったく違うわけです。だから、どんなショットでも欧米人の打ち方を日本人が真似すると、せっかく欧米人にも負けないパワーがある人でも、日本人の強みを活かせず、欧米人の強みにいどむからパワー負けするのです。
そこで、パワー負けするからと、今度は欧米人が鍛えると良い強みの箇所を、日本人なのに鍛えだすプロ選手がいます。だから、上半身はムキムキになって、今度は日本人の強みの一つである俊敏性がそこなわれ、もっと勝てなくなるという悪循環になります。
脱線した気がしますが、大切な最低限の知識なので、頭の隅にいれておいてください。
ですので、欧米選手の真似は絶対しないでください。
もっと正確にいうと、プロ選手のフォームはまったく参考になりませんので、絶対に真似しないでください。

打点でパワーが乗るように足を構えましょうね!
日本人にとって、下半身である足はものすごく重要ですから!!
前足のつま先【重要】
構えたときの前足のつま先は、少し浮かしておきます。
これは、体の造り上、つま先をあげておく方がスムーズに体全体がサーブの動作に入れるからです。
細かい理由は他にいくつもありますが、サーブの動作にスムーズに入れるということだけ知っておいてください。
下の画像を参考にして試してくださいね!

前足のつま先をあげて、かかとだけ着けておきます。
体重は後ろ足に。
前側の足のつま先を上げるので、体重は後ろ足にかけておきます。
こうすることによって、サーブの動作がリズムよく楽にできるようになります。

実は、つま先をあげておくメリットは、他にもいくつもあるんです!
すべてはパワーと安定のため
全身の構え方は、すべてパワーと安定感のために形をととのえます。
できるだけ無駄を省き、最小限の動作で最大限のパワーと安定感を出すのが狙いです。
その基本ができていれば、この先何かの課題があり、もっとパワーを出したいと思ったとき、自分で工夫ができるようになります。
つまり応用ができるようにするためにも、まずはじめは基本を徹底的に習得することが大切です。
レッスンコーチでも、独自の技術を基本かのように教える人がいますが、コーチは子ども達・生徒さん達の見本ですので、絶対によくありません。
そんなコーチに教えてもらうと、才能のある選手しか上手くなりませんし、勝つことができなくなります。
だから、私が教えるまで一回戦も勝てなかった子どもが、1年後には本線に出場できるようになったりします。コーチをしてる間は、独自技術を行なうのではなく、基本技術でテニスをしなければいけません。
野球の元プロ選手が、「コーチは自分のコピーを作ろうとしてはいけない」と、言っていました。その通りだと思います。

基本技術は、すべての技術の母です!
いろいろな応用技術を習得できるようになりますし、また生み出すこともできるようになります!
腕の構え方
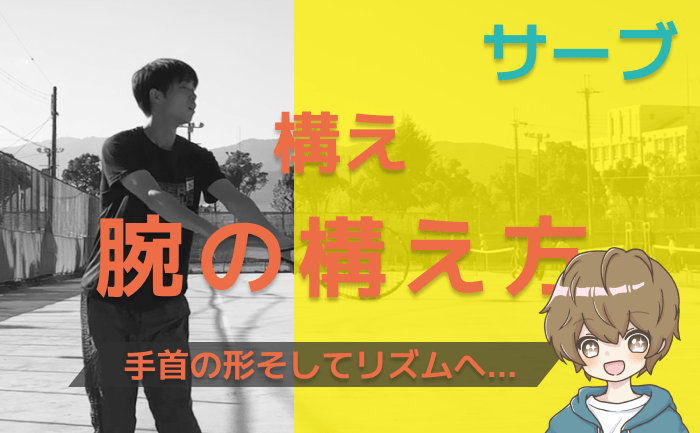

次は、「両腕は体の前」を、みていきましょう!
両腕は体の前
腕の構え方は、人それぞれで大きな違いがあるものではありません。
両腕を体の前にだして構えます。

両腕は、体の前にだして構える。
これは、トスがあげたときに、ラケットを持つ腕も一緒にあげるために、動作しやすいからです。
加えて、人間の腕の造り上、左右の腕が対象に動くか、片方が伸びて片方を引くという動きをすると、自然とパワーを出しやすいという特性があるためです。
簡単な例をあげると、ボールを投げるときや、ボクシングなどの格闘技の動作のとき、片方の腕を伸ばし、反対の腕は「引く」動作をするのは、パワーをだしやすいから。
フォアでも、ラケットを持っていない腕は体の方に引きますね。同じです。
これは、体の力学になります。

すべての技術は、「体の力学」で成り立っています!
この体の力学に合う技術が、正しい技術・怪我をしない技術となります!
手首の角度を決めておく
ラケットを持っている方の手首は、角度を決めておきます。

手首の角度を決めておく。基本は手の甲と腕がまっすぐになるようにします。
注意点としては、手首を手の甲側にそらないようにしてください。
決めておく理由は、動作をしてる間に形を変えると、安定感が悪くなる原因になるからです。
手首の角度は、内に曲げる分には良いですが、曲げすぎもよくありません。逆にそらすのは絶対にしてはいけません。手の甲と腕はまっすぐの状態、つまり少し内に曲げている状態が良いです。
よく言われるのは、回転をかけるためと言われますが、大きな理由は他にあります。
ここでは、皆さんはコーチではないので、詳しい説明は割愛しますね!

なるべく無駄な動作をはぶくことが大切です!
安定感にかかわるからです!
トスとリズムのため
腕を構える上で大切なのは、トスが上げやすいこと・リズムを作りやすいことです。
リズムは、次の「サーブのコツ・その2」で詳しく解説します。ものすごく大切なサーブのリズムを解説しています。
トスは、よく悩むところです。
トスが安定しないのは、よく耳にするところですが、トスも「サーブのコツ・その3」で詳しく解説していますので、興味のある方はご覧ください。リンクを張っておきますね!
構えたとき、トスがあげやすいか、リズムを作りやすいかで、多少の工夫をしてみてくださいね!

腕の構えで大切なのは、トスがあげやすいか、リズムを作りやすいかです!
多少の工夫は、していただいて大丈夫です!
考え方だけ覚えておいてくださいね!
姿勢


次は、「姿勢は逆算した結果の形」を、みていきましょう!
姿勢は逆算した結果の形
構えの形には理由があります。
たとえば、横を向いて構える選手が多い中、前を向いて構えるのを基本とする理由の一つは、トスをあげて、体をひねったときに、「溜め」をつくることができるから。「ひねり戻し」で打ちたいわけです。
「ひねり戻し」は、「肩を入れる理由」の一つで、パワーを生み出すのにとっても大切な基本技術。
はじめから横を向いていると、この「溜め」がつくれません。
その「溜め」を打つときに、解放するから最小限の労力で、最大のパワーが出せるようになります。
そのために、はじめは前を向くわけです。
このようにありとあらゆる技術の逆算の結果が、構えになります。
ですので、構えを見ただけで、効率よくパワーを伝える選手なのか、どうなのかがわかります。
多くの選手は、誰かプロ選手の真似か、楽な姿勢という理由だけで構え方を決めます。
はじめから、〇〇プロがしてるから・横を向いた方が「楽」だからするわけです。つまりしっかりとした理由がない。それでは、良いサーブは打てません。
では、「良いサーブ」というのは、どういうものでしょうか?
これもはっきりとした答えがあり、勝つためのサーブの目的は、「サーブのコツ・その5」で解説していますので、興味がある方はご覧くださいね!

構え方には、勝つための理由があります!
プロ選手によって違う理由
プロ選手や上手い選手は、独特な打ち方(フォーム)をしますね!
なぜなのか、気になりませんか?
詳しく説明します!
技術を習得する段階には、「守破離(しゅはり)」という段階があります。
「守」とは、教えられた基本を忠実に守り、ひたすら教えられた内容を「守る」段階です。
「破」とは、基本を完全に習得して、自分に合うように工夫する段階で、教えられた内容を「破る」段階のこと。
「離」とは、教えられた内容を破り、独自の技術を生み出す段階で、今の常識である独自技術から「離れる」段階です。新しい境地をひらく段階です。
では、プロ選手は、どこの段階の人だと思いますか?
たまに才能だけでプロになって、基本も何もできていなくても、上手く強い選手もいますが、そういう人を「天才」といいます。
コツコツ努力して、プロになった選手を「秀才」といいます。
どちらにしても、「守」の段階ではないのは確かです。
「破」か「離」の段階の人です。
だからこそ、プロ選手のフォームはそれぞれ違います。
何より一番大きな理由は、一人ひとり顔の形・体格が違うように、同じ基本を習得しても、現れるフォームの形は、人それぞれ違うようになります。
ここで大切なのは、基本技術でプレーしていないプロ選手を参考にすると、絶対に上達しないということです。プロ選手の真似を、その人以外の人がしても上達しません。
イチローの真似をしてもイチローにはなりません。
サンプラス・フェデラー・ジョコビッチ・ナダルの真似をしても、逆に怪我したり故障したりしますし、上達しないのと同じです。
これは、すべての人が勘違いするところですので、特に注意が必要です!
必ず基本技術が上達につながります。「破」か「離」の段階の技術の真似をして、怪我や故障、上達を遅れさせないでくださいね!

プロ選手や上手い選手などの技術は真似すると、勝てなくなります!
これは、断言できます!!
まずは基本を大切に
結論として、「守」の段階を徹底して習得することが、上手くなる・強くなる近道。
つまり、基本を徹底して教えてくれるコーチについて、基本を習得することです。
私は教えた子ども達で、上手くなりたい・強くなりたいと思う選手が、運動神経が悪くても上達しなかった選手はいません。
必ず上達します。
ですので、しっかり基本を習得するようにしてくださいね!

基本は、技術だけの問題ではなく、あらゆるモノの土台ですので、何かを習得したいと思ったら、しっかりと「正しい基本」を学べば、何でも上達できます!
まとめ【実話あり】
今回は、「サーブのコツ・構え方」でした。
いかがだったでしょうか?
サーブは、フォアと同じで、色々な形(フォーム)で打てるショットなので、基本を学ぶのが大変ですが、正しい基本を学ぶことができれば、決してむずかしいショットではありません。
ぜひ試してみてくださいね!
ある大阪の大学では、プロ選手がコーチをしてくれています。
私の教え子も、そのプロに教えられたそうです。
しかし…サーブが弱すぎる。
その子が、サーブが弱いと言われると、相談に来ました。
それもそのはず、パワーが伝わられない打ち方で打っているのです。
そこで、ひとことだけアドバイスしました。
「体を止めるな」と。
私が教えた選手でないと、意味がわからないと思いますが、大事は基本なのです。
そのひとことのあと、サーブを一球打った瞬間…
「おおおおおおおおおおお!!!」
と、自分の打ったサーブに驚いていました。
で、なぜ今まで、体を止めて打っていたのか?と聞くと、そのプロにそうしろと言われたからだと答えていました。
私は、散々プロ選手や元プロ選手と話をしてきましたので、まったく驚きませんが、本当にそんなモノなのです。
強く上手いプロ選手になればなるほど、独自の技術やコツを持っていて、その人しかできない技術やコツを、他の選手に教えようとします。
それでは、選手を育てることはできません。
ほとんどの実業団・大学が、この悪循環に気づかず、プロをコーチにしています。
残念な話です。
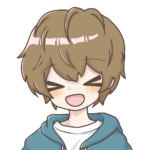
すこしでも、皆さんのテニスライフと人生の役に立てたなら、これほど嬉しいものはありません。
もし、よろしかったら、感想や抱えている問題など、なんでも結構ですのでお問い合わせからご連絡くださいね!
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございます!!