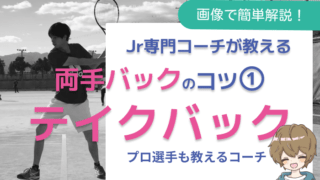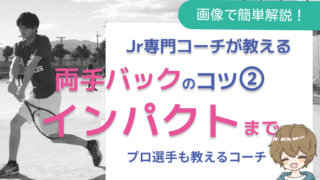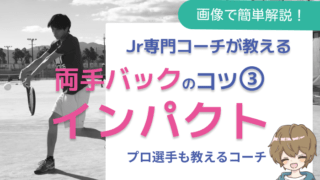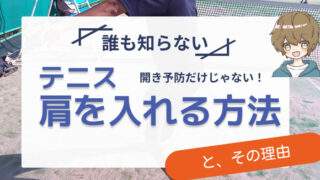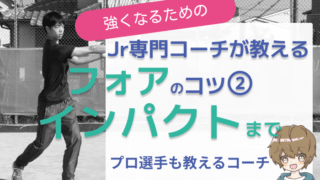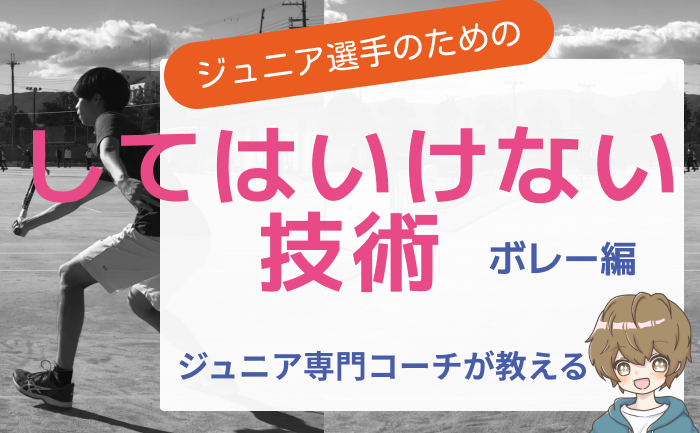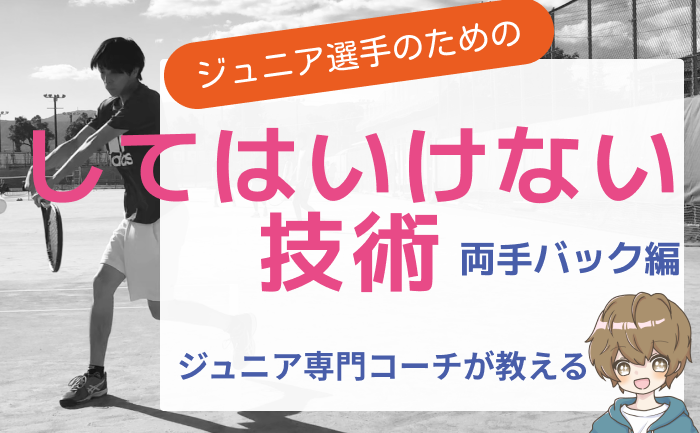
・両手バックが苦手
・両手バックの注意点を知りたい
・両手バックが上手くなりたい
① 両手バックの感覚をつかめる
② 両手バックが安定する
③ 両手バックが上手くなる
④ 両手バックの注意点がわかる
⑤ 両手バックの苦手意識がなくなる
⑥ 両手バックを楽に打つことができる
⑦ 自分の悪い所がわかる
⑧ 両手バックに自信がもてる

こんにちは!ぐっど(@good__tennis)です!
①はじめての教え子はプロ選手に。
②プロ選手の復調を複数人指導した経験あり、得意。
③本戦選手を多数育成。
④小学高学年から、コーチングをする。
⑤選手のメンタル強化も得意。
⑥公立の外部コーチの経験あり。
⑦プロ選手専属のストリンガーの経験あり。
今回は、「両手バックを改善する!」を解説します!
「まとめ」では、「両手バックが苦手だったインカレ選手の実話」を載せています。最後までご覧くださいね!
技術について


ではさっそく「テイクバックを背中側まで引かない」から、みていきましょう!
テイクバックを背中側まで引かない
テイクバックでは、スムーズに打点までラケットが出てくることが最優先です。
テイクバック自体が、パワーを生み出す動作だからです。
それ以上に、パワーを出そうとする必要はないわけです。
だから、テイクバックでは、できるだけリラックスした状態で行ないます。
つまりテイクバックで体のどこかに力が入るようではいけません。
テイクバックで無駄な力が入る代表的な悪い例が、背中側までラケットを引く動作になります。
テイクバックは、体の横(真後ろ)までです。それ以上背中側にひくと安定感を失いますし、良いことがありません。
テニスは、パワーを最優先するのではなく、安定感を最優先に技術の向上を行なうのが、怪我もなく試合を勝ったり、楽しんだりする近道です。
テイクバックの仕方は、インパクトでの手首の形を維持したままテイクバックすると良いです。

背中側に入りすぎると、肩を痛める原因にもなります!
参考となるブログを下記にリンクしておきます!ぜひご覧くださいね!
ラケットは背中側に倒れない
上記のお話に関連して、腕だけではなく、ラケット面が背中側に倒れたり、入ったりするのもデメリットしかありません。
パワーを出せると思っている人が多いのですが、確かに多少のパワーを出すことができますが、安定性やタイミングの取り方に大きなデメリットが出ます。
ほんの少しのプラスを生み出すのに、大きなマイナスを取る人はいませんね。
もっと恐いのは、怪我です。
多くのコーチは、勝つために怪我のリスクを考えませんし、怪我をしても良いとさえ思っているコーチがいます。
でなければ、背中側にラケットを入れることがどれだけ危険かを調べるはずです。
人の体は、背中側に腕や手を持っていくようには作られていません。
全てお腹側で、作業をするようにできています。
つまり無理のある体の動き・使い方です。
何も良いことがありませんので、すぐに修正することが大切。

背中側に、手や腕を入れて、パワーを生み出すことはありません!
サーブでも背中側に手や腕を入れる動きは、絶対にしてはいけません!
故障や怪我につながります!
参考となるブログを下記にリンクしておきます!ぜひご覧くださいね!
面がブレる・開く
テイクバックからフォロースルーまで、ラケット面は一切ブレることなく一定にスイングします。
途中で、ラケット面がブレたり、角度が変わりすぎると、安定感が極端に悪くなります。
両手バックが、安定しない人・苦手な人の多くが、ラケット面がスイング中にブレているから。
練習しはじめは、違和感がありますが、慣れてくると確実に安定感が良くなります。
何よりも、一番はじめに取り組む技術が、ラケットを面を安定されることです。
ただ、「感覚の良い天才」や「才能のある人」は、このラケットを気にすることなく、安定したボールを打つことができます。
とんでもない打ち方をしてるのに、ミスをしないのは、「天才」だからです。
プロ選手の多くがこの天才です。天才でないと、プロ選手にはなかなかなれないから当然です。
つまり、才能があればあるほど、人を教えることができないのは、こういう普通の人が、どこでつまずくのかを自分が体験していないので、教えることができないところにあります。
ブレるとは、どういう形をいうのか、分からない人がほとんどだと思いますし、そういう人はラケット面がブレるなど気にしなくてもいいと、言うかも知れませんね。だって、自分は気にした事がないから。
優秀なコーチは、相手の「できない感覚」を、自分が体験しているように感じられるものです。
だから、どんな選手でも教えることができます。

面がブレる・開くのは、一番に直した方がいいです!
テニスが全く上達しない一番の原因だからです!
参考となるブログを下記にリンクしておきます!ぜひご覧くださいね!
ラケットに反動を付ける
よく見かけるのが、ラケットヘッドに反動(勢い)をつけて、スイングしてしまうこと。
これも、何も良い結果につながりません。
反動をつけるというのは、ムチのようにラケットを振ること。
想像してみてください。
しなるムチを狙ったところに当てるのは、至難の業です。
ラケットに反動をつけるというのは、ムチを当てるのと同じこと。
安定感が、極端に悪くなります。
上記でもお話しましたが、「天才」はできる人がいます。
だから、落とし穴になります。
「天才ではない人」は、そんな芸当はできません。
かなり注意が必要です。

スイングに反動は絶対に使いません!
参考となるブログを下記にリンクしておきます!ぜひご覧くださいね!
打点が体から遠い
両手バックの場合、両手でラケットを持つために、体から横に打点が離れると、パワーが伝わらなくなります。
両手バックの打点は、体に近くて前です。
打点が、体から横に離れるのは、一番いけません。
パワーも安定感もなくなります。
腕やラケットは、打ちたい方向に伸ばす感覚が大切であるために、体の横で打ったり、横に離れると、全く打てなくなります。
走らされて打ったときのことを考えれば、すぐに理解できると思います。
当てるだけになるからです。
両手バックの打点は、思っている打点とは、まったく違うと思います。
バックが苦手な人が多い一番の原因が、この打点が分からないところだと思います。
相当な選手でも、両手のバックの打点を分かっている人は少ないです。
だから、両手バックが打てているように見えてても、本人は納得できていない場合が多い。
では、次で「打点は前」と言われる誤解をお話していきます。
とんでもない人は、真逆のことを教える人がいます。それでは勝てる選手を育てることができません。

両手バックの打点は、本当に難しく、頭で考えていては必ず間違えます!
参考となるブログを下記にリンクしておきます!ぜひご覧くださいね!
前で打つの誤解
打点を前にするときに、常識的な考え方をしていては絶対に打てません。
さらに、「そこまで前で打つことない」という指導者は、全く打点が分かっていません。
体が前に泳いでしまうという状態、つまり体が前のめりになって、打点を前にしようとするのは論外です。
体は、真っ直ぐに保つのは、基本中の基本です。
では、「前」とは、どこのことなのか?
お話していきます。
打点が遅い・後ろなのも、論外です。
打点を後ろにした方が、力が入る錯覚があるのは分かりますが、ボールを打つ感覚で、大切なのはガツンという感覚がないところで打つことです。
ガツンという感覚があるというのは、腕に相手ボールの勢いが伝わっているということで、「ボールの負けている状態」である証拠になります。
両手バックの打点は、皆さんが思っているボール3個分ほど、もっと前の場合がほとんどです。
両手バックの打つ瞬間は、肩が打ち方向へ抜けるような感覚で打ちます。
肩が抜けるようなところが、両手バックの打点。
すると、ボールは力を入れようとしなくても、自然にビュンと軽い打感で打てるようになります。
この正しい打点の場所は、実際に教えてもらわないと、難しいと思います。
一度、両手バックが苦手だというインカレ選手を教えた事がありますが、その人は一瞬で両手バックの感覚を掴んでいました。
やなり才能のある人は、感覚を掴むのが早いなと感心しました。
そのお話は、一番下にある「まとめ」の中に「実話」として書いておきます。
もし興味がございましたら、ぜひご覧くださいね!

両手バックの打点は、ほとんどの人が思っているより、はるかに前になります!
参考となるブログを下記にリンクしておきます!ぜひご覧くださいね!
手首でこねない
打点・インパクトのときに、手首をこねると良くありません。
安定感がまったくなくなるからです。
手首をこねてしなう原因は、打点でラケット面を修正しようとするからですが、この根本原因はテイクバックにあります。
正しいテイクバックができていないと、ラケット面を操作して、飛ばしたいボールにしようとします。
これが原因で、打点で手首をこねてしまうことになります。
他の原因としては、打点が遅れたことや前過ぎたことによる修正です。
しかし、この場合、テイクバックが正しければ、必要な修正である場合がほとんどです。
遅れてしまったのは仕方のないことなので、修正しないとミスになりますから。
できるだけタイミングを合わせて打つことが大切になります。
しかし技術練習では、遅れても手首で修正するのは良くありません。正しい打点で、正しい打ち方ができないときは、そのままミスをする方が早く上達します。
試合では仕方がありませんが、練習ではミスをしても小手先で修正しないようにすることが大切です。

フォームを変えて、小手先のテクニックでミスしないようにするのは上達を遅らせます!
体の使い方について


では次は「壁をつくる」を、みていきましょう!
壁をつくる
「壁をつくる」という技術を、知らない人がほとんどだと思います。
相当なコーチでも知らないと思います。
「壁」とは、肩・腰・膝が、壁のように動かない「溜め」ができている状態を言います。
これが、日本人がパワーを最大に出す源になります。
壁が崩れた状態で打つと、ボールにパワーを載せるのに、しんどくなります。
逆に壁ができている状態ですと、ボールにパワーを伝えるのが大変楽になります。
テイクバックをして、打つ準備に入るとき、誰もが「肩」を意識しますが、日本人にとって肩はそれほど重要ではありません。
その証拠に、ほとんどのプロ選手であっても、「肩を入れる」本当の技術は全くできていません。
下に「肩の入れ方とその理由」のブログのリンクを貼っておきますでの、興味がある方はぜひご覧ください。
肩よりも膝と腰の方が、日本人がパワーを生み出すのには、大変重要になります。
この壁ができているかどうかで、ボールのパワーが全く違ってきます。
壁をつくる詳しい解説ブログをまた作成しますので、しばらくお待ちください!
参考までに、フォアに関する壁のつくり方を、下記にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧くださいね!

壁をつくるのは、ボールを打つスポーツをする上で、基本中の基本です!
ですが、テニスではできている人、知っている人はほとんどいません…。
体は真っ直ぐ
両手バックに限らずですが、テイクバックからフォロースルーまで、傾いたり、よじれたりしてはいけません。
「溜め」をつくるための、「ねじれ」と、体の使い方が間違っている「よじれ」は、全くの別物です。
「よじれ」は、上半身と下半身が、連動していない状態で、バラバラになっている状態をいいます。
特に多い両手バックの「よじれ」は、上半身が少し背中側に倒れて前かがみになっている状態です。
これでは、パワーも安定感もでません。
上半身は、下半身にドシッと乗せておくことが、日本人がパワーを生み出す土台です。
上半身よりも下半身のパワーをボールに乗せないといけません。
体幹のパワーを動きや打点で活かせるのは、欧米人のように上半身に重心がある場合です。
日本人や東洋人は、体幹よりも下半身が大切。
日本人の強みを使わずに、欧米人の強みで勝負するからパワー負けを起こします。
野球やゴルフで、パワー負けなんてほとんど聞いたことがありません。
それは、下半身を大切にするから。
下半身を意識して、上半身は下半身に合わせるだけにし、体全体が下半身に連動するようにします。
そこで、体の「よじれ」が障害になります。
上半身は真っ直ぐにして、下半身の邪魔をしないようにします。

体幹体幹と今の時代ではいいますが、民族特有の原理原則である基本を無視しても勝てません。
結果がちゃんと示していますね!
利き手で引っ張らない
基本の話をしますが、利き手側であるラケットのグリップ側(下側)にある利き手でラケットを振ってはいけません。
ラケットをしっかりと振れなくなるからです。
両手バックは、右利きの人は左の腕を「主」として主導させ、右の腕は「従」で左腕に従うようにします。
つまり語弊はありますが、左腕は、グリップを軽く握るだけの状態ですね。
右利きの人は、左腕でスイングするようなイメージ。
力関係の割合は、左腕が8、右腕が2で、左腕でスイングします。

基本的なことですので、知っている方も多いと思います!
かかとから付く
これは踏み込むときの足の使い方です。
踏み込む足を、つまさきからコートに着地してはいけません。
必ずかかとかた着地します。
ボールを打つタイミングに合わせてつま先へ体重を移動させ、打点に体重を移動させるようにします。
つま先から着地すると、体重がスムーズに移動しなくなるのと同時に、タイミングを合わせにくくなるので注意しなくてはいけません。
余談ですが、バックでスライスを打つときに、止まってから打つと教える人がいます。
これは絶対に良くありません。
遊びでテニスをしている人なら良いですが、勝ちたいと思っている人は決してやってはいけないものの一つです。
特にバックを両手で打つ人は、バックのスライスを打つという選択肢は、ほぼありません。
それは、スライス自体が弱くて攻められやすいショットだからです。
それに加えて、「止まってから打つ」というのは、体重移動をせずにスライスを打つことで、ただでさえ弱いスライスをさらに弱くすることになります。
初心者の方に、スライスの感覚を覚えてもらうためなら、仕方がないというレベルですが、それでも逆にタイミングが取りづらくなり、あまり良いアドバイスとは言えません。

踏み込んだ足の使い方は、意外に大切です!
ここを改善できれば、タイミングが取りやすくなります!
その他


では次は、「回り込んで打つことはない」を、みていきましょう!
回り込んで打つことはない
両手バックに限らず、バックに回り込んで打つことは決してありません。
わざわざパワーの乗らないショットを選択しないからです。
回り込むのは、必ずフォアだけ。
バック側に回り込んだ時点で、弱いボールになると同時に、フォアが苦手なのが分かりますし、バック側に回り込んでも戦術的に攻め方の範囲を狭くするからです。
たとえ、フォアよりもバックの方が得意であっても、回り込んでバックを打つことは決してありません。
上記と同じ理由からです。
ですので、特に勝ちたいと思っている選手は、回り込んでバックを打つことがないように注意が必要です。

回り込んでバックを打つ選択肢は、絶対にありません!
バックはフォームが決まっている
両手バックでも片手バックでも、バックは打ち方が限られています。
この打ち方以外、パワーと安定感を両立させる打ち方がないという打ち方があります。
ですので、バックは実は非常に簡単なショットです。
とはいえ、一般的にはバックを苦手としている人が多い。
これは、単純に打っている数が、フォアよりも断然少ないからです。
何度も何度もボールを打つことによって、上手い下手はおいといて、苦手意識は徐々に薄れてきます。
ですので、なるべく正しい打ち方で、体がなれるように練習することが、強くなるにしても、楽しむにしても、また怪我をしないという面からでも大切になります。
せっかくテニスは怪我や故障が少ないスポーツなのに、打ち方の間違いで怪我や故障をするのは、面白くないですから。

バックの打ち方は、限られています!
なるべく正しい打ち方で打てるようにしてくださいね!
バックが打てる気がしない理由
まずバックは打つ数が極端に少なくなるショットです。
単に打つ数を多くするだけでも、だんだん打てるようになってきます。
はじめは、バックを打つ数を意識的に増やしてみてください。
練習では、数を打つために回り込んでバックを打っても大丈夫です。
試合でしてはいけないだけですから。
次に、バックは一般的に考えているような打ち方ではないことが挙げられます。
イメージがしにくいことは、実際に行なうのが難しいのと同じで、打てるイメージができないものは、実際に打ってみても打てないです。
まずは、正しいバックをしっかりしたコーチから学び、イメージを付けるようにすれば、意外に簡単にバックは打つ事ができます。
テニスのバックは、ショットの中でも一番簡単です。
打ち方が限られているから。
打ち方ももちろん、「感覚」を教えてもらえるような優秀なコーチから学ぶと、簡単に打てるようになるショットですので、根気よく頑張ってみてくださね!

バックは本当に簡単ショットなんです!
まとめ【実話あり】
今回は、「両手バックの注意点」でした。
いかがだったでしょうか?
皆さんがテニスを通じて、人生が豊かになるように願っています!
あるインカレ選手は、両手バックのスピンを打つのが大の苦手で打てませんでした。
それは、全くスピンの感覚が掴めなかったからです。
バックを教えるのは、非常に簡単で、教えるのに苦労した経験がありません。
ですので、まずはその選手にイメージを付けるために、言葉だけで説明することにしました。
まずイメージを付けて、実際に打ったときの感覚のズレを、反復練習によって徐々に修正するのが、私の王道の練習の仕方だったからです。
そして、両手バックのスピンの感覚を話していると…
その人は、「あ!打てる気がする…」と独り言をいいました。
極稀に、私の言葉を聞いただけで、打てるようになる人がいます。
特に、天才肌の人が多いです。
他には、小学5年生の子が、サーブを打つときに、言葉だけの説明で凄いサーブを打てるようになった選手がいました。
しかし、そういう選手は、一旦私が教えなくなると、すぐに打てなく選手が多い。
これは、その選手の感覚を知って、教えられるコーチがいないから、起こる現象です。
私は、その選手の感覚を、自分の感覚のように知る訓練をさせられて育っているので、得意です。
ですので、天才肌の選手を教えるのは、私にとってものすごく簡単です。でも、教える面白さがないんですけどね…。すぐできてしまうので。笑
そのインカレ選手も、
ボールを一発打った時点から、完璧に両手バックのスピンを打っていました。
数をこなすにつれて、どんなボールに対しても完璧。フラットは元々得意なので、打ち分けるようにまでなりました。まぁ…
才能のある天才肌の選手は、やっぱり凄いですね。
私からすると、コーチングとしては、面白くない選手の部類です。笑
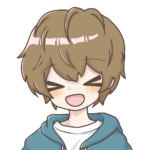
すこしでも、皆さんのテニスライフと人生の役に立てたなら、これほど嬉しいものはありません。
もし、よろしかったら、感想や抱えている問題など、なんでも結構ですのでお問い合わせからご連絡くださいね!
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございます!!